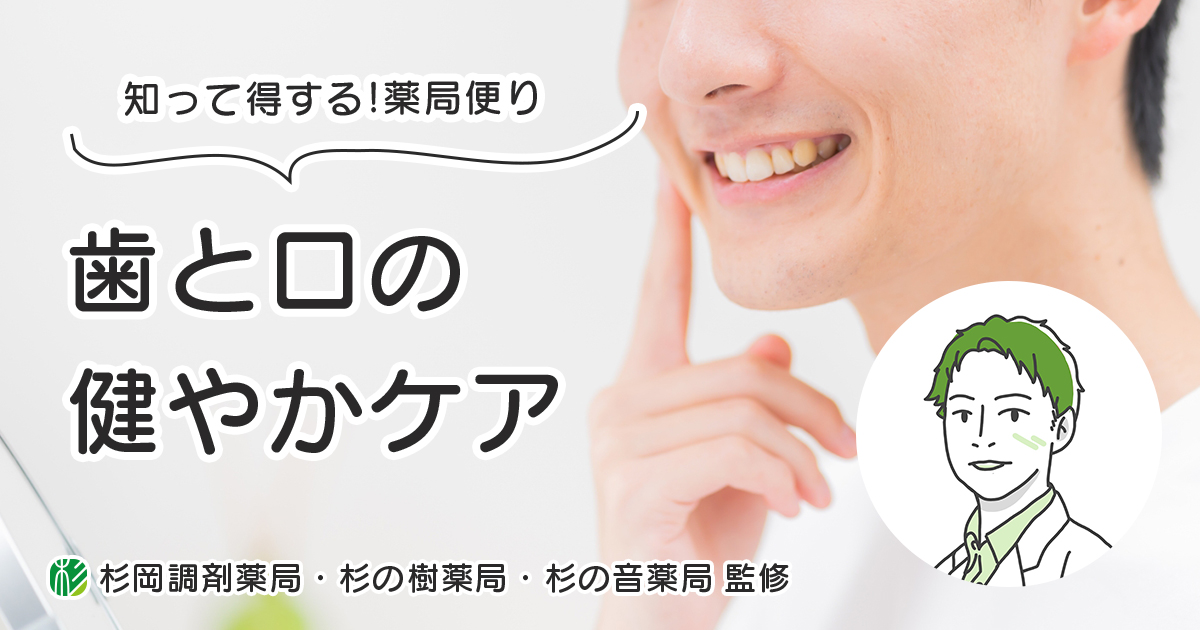歯と口のケアを怠ると歯周病やむし歯になって、ついには歯を失うことに。すると咀嚼能力が低下し、栄養摂取に問題が。口もとが気になって、人との会話を楽しめなくなることも。健康で笑顔あふれる毎日は歯と口のケアから始まります。
気になるトピックス8
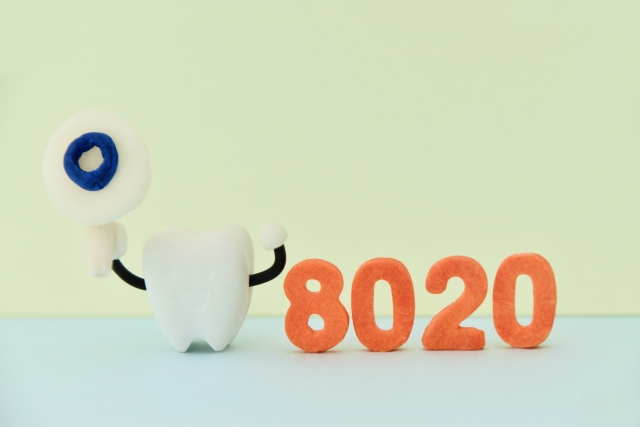
歯や口に関するホットな話題をピックアップ。
①8020運動が浸透
少なくとも20本の歯があれば、80歳になっても食べる機能を満たすということで1989年に始まった「8020運動」。当初の達成率は7%程度でしたが、今では51.2%にも増加しています。
②日本人の7割が歯周病
厚生労働省の調査では、歯周ポケットの深さが4mm以上ある進行した歯周病の人の割合は60歳以上では5割以上。軽症の人も含めると、日本人の7割が歯周病と推定されています。
③口の中の細菌は寝ている間に増える!?
就寝中は口を動かすことが少なくなり、洗浄作用や殺菌作用などがある唾液の分泌が減少。そのため口腔内の細菌が繁殖しやすくなります。寝る前にしっかりと歯磨きを。
④赤ちゃんにはむし歯がない?
胎内は無菌なので生まれたばかりの赤ちゃんの口の中にはむし歯菌はいません。しかし乳歯が生えてくると、周りの大人から感染しやすくなります。食べ物の口うつしなどは避けましょう。
⑤歯周病と糖尿病の深い関係
高血糖状態が続くと免疫細胞の働きが低下し、歯周病菌に感染しやすくなります。一方、歯周病菌の毒素などはインスリンの作用を弱め、糖尿病が悪化。両者は相互に悪影響を及ぼします。
⑥大人のむし歯「根面う蝕(こんめんうしょく)」に注意
加齢や歯周病により歯茎が下がると歯の根元がむき出しになります。そこに発症するむし歯が根面う飴です。歯の根元は磨きにくく、また酸によって溶けやすいことが主な原因です。
⑦歯ブラシで落とせる歯垢は約60%
むし歯や歯周病を引き起こす原因となる歯垢。しかし歯ブラシだけで落とせるのは60%程度。デンタルフロスも利用すると80%に、さらに歯間ブラシを加えると85%にアップします。
⑧オーラルフレイルとは
オーラルは「口腔の」、フレイルは「虚弱」という意味。オーラルフレイルは噛む、飲み込む、話すといった口腔機能の軽微な衰えことで、老化の始まりを示すサインといわれています。
基本の3つの習慣

健康な口腔環境を保つために身につけておきたい基本習慣。今日からぜひ取り組みましょう。
おいしいものを食べ、人との会話を楽しむ。いつまでもこうした豊かな人生を送りたいもの。そのために赤ちゃんからお年寄りまで実践したい歯と口のケアを具体的にご紹介します。
①食べたら磨く
食事をすると口の中は酸性に傾き、歯の成分のミネラルが溶け出す「脱灰(だっかい)」が起こります。 その後、唾液が脱灰した歯を修復(再石灰化)しますが、唾液による再石灰化が不十分なことも。食後、歯磨きをして口の中を中性に戻しましょう。
むし歯や歯周病から歯を守るには毎日の歯磨きが何よりも大切。
②間食は時間と回数を決める
何回も間食をしたり、甘いものを飲んだりしていると、口の中は酸性に傾いたままとなり、歯の成分はどんどん溶け出します。むし歯の原因となるので、だらだら食いは避けましょう。どうしても間食をしたいときは時間と回数を決めて。
③3~6ヵ月に1回はプロのケア
どんなに丁寧に歯磨きをしても磨き残しはあり、そこに歯垢がたまってきます。定期的に歯科でチェックを受け、必要に応じて歯垢を除去してもらいましょう。むし歯や歯周病の早期発見・早期治療の機会にもなります。
歯のケアでおいしく楽しく
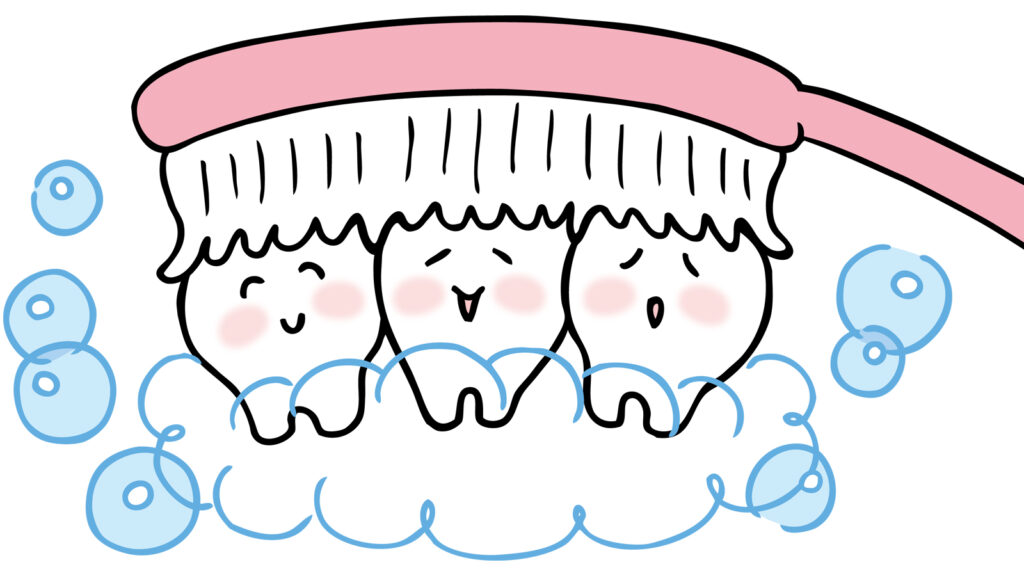
むし歯や歯周病から歯を守るには毎日の歯磨きが何よりも大切。1本1本丁寧に磨きましょう。
●歯ブラシの使い方を見直そう
歯の汚れの除去には、歯の表面を物理的にこすり取ることが必要。そのための道具が歯ブラシです。
①歯ブラシの選び方
基本的には自分にとって使いやすいもの、気に入ったものでOKです。なお、毛が硬すぎると歯茎を傷つけることがあるので軟らかめがおすすめです。電動歯ブラシを利用する際は、歯ブラシを歯にしっかりと当てることを心がけて。
②歯ブラシの持ち方と力加減
鉛筆を持つときと同じように持ちましょう。歯ブラシを強く歯に押し当ててゴシゴシと磨くとブラシの 毛先が開いてしまい、かえって汚れが落ちにくくなります。歯茎を傷つけることもあるので、力を入れすぎないようにしましょう。
③歯磨きの基本
それぞれの歯のすべての面を丁寧に磨きます。そのためには歯ブラシの角度を変えて、歯の面にきちんと毛先が当たるように工夫しましょう。磨く順番を決めて、一巡するように磨くと磨き残しが少なくなります。
④交換のタイミング
毛先が開くと、歯の汚れを落としにくくなります。歯ブラシのヘッドを裏側から見て、毛先がはみ出していたら、新しい歯ブラシに取り替えて。気に入った歯ブラシを見つけたら、数本買いおきしておくのもよいでしょう。
●プラスで使おう

通常の歯ブラシでは除去しにくい汚れには、歯ブラシを助ける道具が役立ちます。
①フロスの使い方
切って使うタイプと柄のついたタイプがあります。フロスを歯と歯の間にゆっくり入れ、歯の側面を前後、あるいは上下に動かします。使い方を誤ると歯茎を傷つけることがあるので歯科で指導を受けるとよいでしょう。
②歯間ブラシの使い方
歯と歯の間に入れて前後に動かします。ただし、無理やり入れないこと。歯茎を傷つけ、歯と歯の間にある歯間乳頭という歯茎部分が下がる原因となります。すき間の広さに合わせて、強い抵抗がなく動かせるサイズを選びましょう。
③歯垢のたまりやすい場所はより丁寧に
歯と歯茎の境目、歯と歯の間、 奥歯のかみ合う面、歯並びが悪いところなどは磨き残しが多く、歯垢がたまりやすい場所。こうした場所は特に意識して丁寧に磨きましょう。歯磨き後に歯垢染色液でチェックするのもおすすめ。
④歯磨き剤は目的に合わせて
「口臭予防」「ホワイトニング」など 効能を強調した歯磨き剤がいろいろ出ているので、目的に合わせて選びましょう。市販品の90%以上がむし歯予防に役立つフッ素を配合。最近は1,450ppmという高濃度の製品も出ています。
⑤子どもの歯のケアのポイント
幼いうちから歯ブラシを使って歯磨きの習慣をつけることが大切ただし、小学校3年生ぐらいまでは 自分磨きだけでは不十分なので、 保護者が仕上げ磨きをしましょう。その際、歯茎を傷つけないように優しく磨くことが大切。
⑥義歯のケアもしっかりと
義歯は歯の代わりをするものなので、歯と同じようにブラシで磨いたり、義歯専用の洗浄剤を利用したりして手入れをしましょう。表面に細菌が付着したまま装着すると、義歯が当たった粘膜が炎症を起こすこともあります。
口のケアでおいしく楽しく

口の健康の維持に重要な役割を果たす唾液。唾液をしっかり出すように心がけましょう。
●よく噛んで食べる
よく噛むことで、あごや歯茎が鍛えられ丈夫になります。また、噛めば噛むほど唾液の分泌量が増えます。唾液は口の中の汚れを洗い流してむし歯や歯周病を予防したり、細菌やウイルスを殺菌するなど、さまざまな働きがあります。
●唾液腺マッサージ
耳下腺、顎下腺、耳下腺の「三つの唾液腺」を刺激しましょう。
両手を顔に当てて、ゆっくり と円を描くよう にマッサージ。 前回し、後ろ回し各5回。
耳下腺:両手を頬に当てて、ゆっくりと円を描くようにマッサージ。前回し、後ろ回し各5回。
顎下腺:親指をあごの骨の内側の柔らかい部分に当て、耳下からあご先までら5か所ほど刺激。各5回ずつ。
舌下腺:両手の親指をあごの下に当て、つき上げるようにゆっくり10回押します。
●健「口」体操
口の周りの筋肉を動かすことで、舌がよく動くようになり、唾液の分泌が促されます。また、オーラルフレイルの予防にもなります。さらにフェイスラインがすっきりする効果も期待できます。
両目をしっかり閉じたら、口を閉じて口角を上げます。
両目を大きく開き、上方を見ながら、口を大きく開きます。
口を閉じ、舌先で唇の内側を左回り、右回りになめます。
口腔内にたまった唾を勢いよくゴックンと飲み込みます。
舌をしっかり前に出し、そのまま10秒間キープします。
●禁煙のすすめ
タバコの煙に含まれるニコチンにより免疫力が低下し、歯周病菌が繁殖しやすくなります。喫煙時に口腔内の温度が上昇すること も、歯周組織に悪影響を及ぼすといわれています。
●かかりつけ歯科医師をもとう
かかりつけ歯科医師に定期的に口の中を診てもらうと、小さな変化にも気づいてもらいやすくなります。かかりつけ歯科医師をもっている人はもっていない人より平均寿命が長いとの報告も。
Keep on smiling!
公式キャラクター「スマイリー」による生活を彩るinstagramもチェック!!
引用
“引用文献:classA Life”